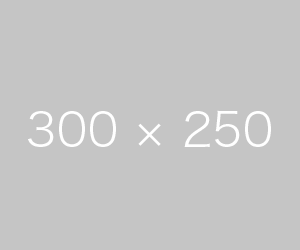結論:沖縄黒糖の原材料「さとうきび」は、特有の気候と手間ひまかけた栽培によって育まれ、黒糖の深い味わいを支えています。
・品種には用途ごとの特色があり、風味に違いが生まれる
・栽培には長期間かかり、成長を見守る手間が必要
・収穫は年に一度、短期間に集中して行われる
・地域の農業や文化に深く根ざした存在
沖縄黒糖を支える「さとうきび」の実像に迫る
沖縄のさとうきびとは?
・暖かい気候・日照時間の長さ・ミネラルを含む土壌が栽培に最適
・黒糖用さとうきびは糖度が高く、香りも強いのが特徴
沖縄では、さとうきびはただの農産物ではなく、地域経済と食文化を支える重要な作物です。主に黒糖製造用として使われる品種は、収量と糖度のバランスに優れた「NiF8号」などが代表的。品種ごとに風味や食感が微妙に異なり、それが黒糖の個性として表れます。
栽培方法:自然との対話が不可欠
・台風や乾燥への対策が重要
・除草・追肥・根本管理など、人の手が多く入る
さとうきびの栽培には多くの時間と労力がかかります。苗の植え付けから始まり、追肥や除草といった定期的な管理作業が欠かせません。沖縄特有の強い日差しはさとうきびの成長に適している反面、台風や乾燥といったリスクも伴います。農家の方々は自然と向き合いながら、最良の黒糖を生み出すために日々努力しています。
収穫の裏側:年に一度の大仕事
・機械収穫が主流だが、急斜面などでは手作業も
・刈り取ったさとうきびはすぐに製糖工場へ搬送される
収穫は糖度が最も高まる冬の時期に集中して行われます。時間との勝負となる収穫作業は、早朝から行われることも多く、地域総出で手伝う光景も見られます。収穫されたさとうきびは新鮮なうちに搾汁されなければならないため、迅速な搬送体制が整っており、これが黒糖の品質維持に繋がっています。
黒糖づくりとの関係:さとうきびが味の決め手
・品種や土壌によって黒糖の色やコクに違いが出る
・さとうきびそのものの品質が、黒糖の品質を決定づける
黒糖は、さとうきびの絞り汁を煮詰めて固めた極めてシンプルな食品です。そのため、原料となるさとうきびの品質がすべてを左右します。風味豊かな黒糖をつくるためには、糖度が高く、アクの少ないさとうきびが必要とされており、これはまさに農家の技術と沖縄の自然が生み出す結晶なのです。
まとめ
沖縄の黒糖がおいしい背景には、「さとうきび」の力が欠かせません。その魅力は次のようにまとめられます。
・沖縄の自然環境が栽培に適している
・手間を惜しまない丁寧な栽培と管理
・収穫はスピードと連携が求められる一大イベント
・黒糖の味と品質は、さとうきびでほぼ決まる
これらの要素が合わさって、海邦商事をはじめとする沖縄の黒糖メーカーが、他にはない味と香りの黒糖を作り出しているのです。